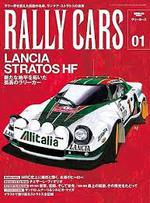2010年04月28日
皐月の鴨川納涼床開き間近

今日の京都はお天気が最高でまだ少し早いのですが五月晴れという言葉がピッタリの一日でした。お友達のKさんの仲良し4人の手作り作品展が祗園のギャラリー祗園小舎で開かれているので見に行ってきました。神戸からも友達2人が来て、束の間でしたが楽しい時間を過ごすことが出来ました。桜が葉桜になり、新緑が目に眩しい気持ちのよいお天気でした。四条大橋を歩いていると鴨川の右岸に納涼床が出来ており、あと三日もすれば、「皐月の床開き」かと思いながら東山の新緑を眺めていました。GWに入るとこの床が日が落ちる時刻になると人で一杯になります。五月(さつき)の風景ですね。北は二条大橋から南は五条大橋までの約2.5キロの間に98軒もの床が出揃います。

納涼床は祇園祭とともに京の夏の風物詩です。

江戸時代の納涼床の風景画です。夕涼みと言うか涼を求める人々で賑やかな様子が覗えますね。
Posted by フェラリーの翼 at
23:57
│Comments(0)
2010年04月26日
人間にとって時間とは
光陰矢のごとし
時間は私達にとって大変大事なもの?であります。銀閣寺の執事長、平塚景堂師が「座禅は、時間というものが人間から離れて勝手に流れゆくのを阻止する力を養うものであろう。時間は、わたしたち人間存在そのものであり、日々の暮らしの質のことである。わたしたちが自分を見つめることなしに、目前の欲求を満たすのみの空疎な暮らしをするなら、時間はわたしたちと無縁のところを矢のように通り過ぎてゆくのである。人間はつい楽な方へと流れる。それは今日を生きることではなく自分を無制限に先送りすることである。そこに真に生きた時間はない。」と新聞の記事で述べられておりました。人間は誰しも子供の頃は悩みや辛いことは、あまりなかったので、時間というものを意識せずに過ごしていたと思います。しかし大人は違います。時間に翻弄され、還暦の頃に過去を振り返ってみると時間は浦島太郎のように過ぎ去っていたと思うのではないか。平塚師の記事の最後に「人間の一生とは今日一日のことなのである。今日一日に本心が無ければ、自分の一生といえども他人事となってしまうであろう。」と結ばれておられました。この考え方は、千日回峰行の酒井雄哉師も同じ事を自身の著書で述べられておられました。
時間は私達にとって大変大事なもの?であります。銀閣寺の執事長、平塚景堂師が「座禅は、時間というものが人間から離れて勝手に流れゆくのを阻止する力を養うものであろう。時間は、わたしたち人間存在そのものであり、日々の暮らしの質のことである。わたしたちが自分を見つめることなしに、目前の欲求を満たすのみの空疎な暮らしをするなら、時間はわたしたちと無縁のところを矢のように通り過ぎてゆくのである。人間はつい楽な方へと流れる。それは今日を生きることではなく自分を無制限に先送りすることである。そこに真に生きた時間はない。」と新聞の記事で述べられておりました。人間は誰しも子供の頃は悩みや辛いことは、あまりなかったので、時間というものを意識せずに過ごしていたと思います。しかし大人は違います。時間に翻弄され、還暦の頃に過去を振り返ってみると時間は浦島太郎のように過ぎ去っていたと思うのではないか。平塚師の記事の最後に「人間の一生とは今日一日のことなのである。今日一日に本心が無ければ、自分の一生といえども他人事となってしまうであろう。」と結ばれておられました。この考え方は、千日回峰行の酒井雄哉師も同じ事を自身の著書で述べられておられました。
Posted by フェラリーの翼 at
22:52
│Comments(0)
2010年04月26日
編み機のゲージて何の事?
ゲージとは編み機の針数の密度のことを言います。
1インチ(約2.54cm)間にある針数で呼称されています。目の粗さでは、例えば7ゲージと14ゲージとでは7ゲージの方が目が粗いのです。また横編み機の場合は1.5ゲージから20ゲージまで11種類のゲージがあります。ニット業界で一般的に使われている編み機はSES102(7ゲージ)とSES122(12ゲージ)のものです。家庭用の編み機の場合は、6ゲージの機械が主に使われています。1.5ゲージ~7ゲージをローゲージ、12ゲージ~20ゲージをハイゲージを呼びます。そしてこれらの中間をミドルゲージとしています。
1インチ(約2.54cm)間にある針数で呼称されています。目の粗さでは、例えば7ゲージと14ゲージとでは7ゲージの方が目が粗いのです。また横編み機の場合は1.5ゲージから20ゲージまで11種類のゲージがあります。ニット業界で一般的に使われている編み機はSES102(7ゲージ)とSES122(12ゲージ)のものです。家庭用の編み機の場合は、6ゲージの機械が主に使われています。1.5ゲージ~7ゲージをローゲージ、12ゲージ~20ゲージをハイゲージを呼びます。そしてこれらの中間をミドルゲージとしています。

Posted by フェラリーの翼 at
00:03
│Comments(0)
2010年04月26日
編み機のゲージて何の事?
ゲージとは編み機の針数の密度のことを言います。
1インチ(約2.54cm)間にある針数で呼称されています。目の粗さでは、例えば7ゲージと14ゲージとでは7ゲージの方が目が粗いのです。また横編み機の場合は1.5ゲージから20ゲージまで11種類のゲージがあります。ニット業界で一般的に使われている編み機はSES102(7ゲージ)とSES122(12ゲージ)のものです。家庭用の編み機の場合は、6ゲージの機械が主に使われています。
1インチ(約2.54cm)間にある針数で呼称されています。目の粗さでは、例えば7ゲージと14ゲージとでは7ゲージの方が目が粗いのです。また横編み機の場合は1.5ゲージから20ゲージまで11種類のゲージがあります。ニット業界で一般的に使われている編み機はSES102(7ゲージ)とSES122(12ゲージ)のものです。家庭用の編み機の場合は、6ゲージの機械が主に使われています。
Posted by フェラリーの翼 at
00:03
│Comments(0)
2010年04月23日
一冊の本 「一日一生」 酒井雄哉師の人生訓
 比叡山の延暦寺、天台宗独自の荒行「千日回峰行」2回満行された酒井雄哉老師の著書です。千日回峰行は、天台密教の中で荒行中の荒行です。生死をかけて行われます。行の中身は、まず12年間籠山した後、約7年間かけて1000日の間、行われます。最初の3年間は、1年のうち100日、1日30kmを歩き255ヶ所の霊場を巡拝し、後の2年間は1年に200日、同じ行を行い、5年間で700日地球一周と同じ距離(4万キロ)を歩きます。この行を終えると次に「堂入り」という生死に係わる行を行います。堂入りとは、9日間「断食、断水、不眠、不臥」で明王堂にこもり、十万遍の不動真言を唱え、不動明王と一体になる行を満じるのです。私は酒井老師が千日回峰行のドキュメントを20代の時NHKのTVで見ました。そしてその時思ったのは、この行は生死をかけて、人間の精神力の限界を超えた修行だと感激しました。酒井老師は2度千日回峰行を満行されました。天正年間(16世紀末)以来、僅か3人のみが2度満行し、そのお一人が酒井師なのです。故に”生き仏”と呼ばれておられるのです。酒井老師の書かれたこの本は、スピード化の現代社会で、とかく忘れがちな自分自身の生き方を考える時間を与えてくれるヒントがいっぱい書かれている一読する価値のある本だと思います。現代を生きる私達は仕事に翻弄され、自分を見つめる事を忘れていませんか。生きているのか。生かされているのか。考える時間も必要だと思います。
比叡山の延暦寺、天台宗独自の荒行「千日回峰行」2回満行された酒井雄哉老師の著書です。千日回峰行は、天台密教の中で荒行中の荒行です。生死をかけて行われます。行の中身は、まず12年間籠山した後、約7年間かけて1000日の間、行われます。最初の3年間は、1年のうち100日、1日30kmを歩き255ヶ所の霊場を巡拝し、後の2年間は1年に200日、同じ行を行い、5年間で700日地球一周と同じ距離(4万キロ)を歩きます。この行を終えると次に「堂入り」という生死に係わる行を行います。堂入りとは、9日間「断食、断水、不眠、不臥」で明王堂にこもり、十万遍の不動真言を唱え、不動明王と一体になる行を満じるのです。私は酒井老師が千日回峰行のドキュメントを20代の時NHKのTVで見ました。そしてその時思ったのは、この行は生死をかけて、人間の精神力の限界を超えた修行だと感激しました。酒井老師は2度千日回峰行を満行されました。天正年間(16世紀末)以来、僅か3人のみが2度満行し、そのお一人が酒井師なのです。故に”生き仏”と呼ばれておられるのです。酒井老師の書かれたこの本は、スピード化の現代社会で、とかく忘れがちな自分自身の生き方を考える時間を与えてくれるヒントがいっぱい書かれている一読する価値のある本だと思います。現代を生きる私達は仕事に翻弄され、自分を見つめる事を忘れていませんか。生きているのか。生かされているのか。考える時間も必要だと思います。 
Posted by フェラリーの翼 at
21:58
│Comments(0)
2010年04月20日
没後400年特別展覧会 長谷川等伯展は2回見に行こう。
京都国立博物館で5月9日(日)まで開催中 

この展覧会は2度楽しめます。その訳は期間中、前期(4月25日まで)と後期(4月26日~5月9日)に分かれており、前後期で展示作品の一部入れ替えがあります。

長谷川等伯は能登(石川県)の出身で狩野永徳と並び桃山時代を代表する絵師です。狩野永徳率いる狩野派と対抗し自ら雪舟五代を名乗り、長谷川派のトップとして安土桃山時代から江戸時代の初期に活躍しました。能登の頃は、長谷川信春として絵仏師として仏画を中心に描いていました。30代に妻子とともに上京し、等伯と名乗り、時代を代表する絵師となったのです。


この展覧会は2度楽しめます。その訳は期間中、前期(4月25日まで)と後期(4月26日~5月9日)に分かれており、前後期で展示作品の一部入れ替えがあります。

仏涅槃図

長谷川等伯は能登(石川県)の出身で狩野永徳と並び桃山時代を代表する絵師です。狩野永徳率いる狩野派と対抗し自ら雪舟五代を名乗り、長谷川派のトップとして安土桃山時代から江戸時代の初期に活躍しました。能登の頃は、長谷川信春として絵仏師として仏画を中心に描いていました。30代に妻子とともに上京し、等伯と名乗り、時代を代表する絵師となったのです。
Posted by フェラリーの翼 at
17:29
│Comments(0)
2010年04月18日
春の一日 京都 西陣界隈で大人の課外授業
異業種交流と西陣界隈散策・・・自分で作ったあられ美味しかった!  17日の土曜日異業種交流で京都西陣界隈で大人の課外授業をしました。まず最初に訪れたのは、菓匠、茶房、上枝物あられ処「宗禅」です。ここであられ作りを体験しました。築120年の町屋での「あられ作り」です。
17日の土曜日異業種交流で京都西陣界隈で大人の課外授業をしました。まず最初に訪れたのは、菓匠、茶房、上枝物あられ処「宗禅」です。ここであられ作りを体験しました。築120年の町屋での「あられ作り」です。 
このお店、ただのあられ屋さんでは、ありません。京都の洛北で400年以上の歴史のある料亭「山ばな平八茶屋」との合作で誕生した店です。素材のこだわりは、半端ではありません。この日あられ作りの体験をした後に頂いたのは、この店でしか食べられない絶品の「ぶぶ漬け」でした。一般でいうお茶漬けです。
素材は天然の真鯛と国産の鰻で平八茶屋で作られた逸品です。あられは、帆掛けの宝船をかたどっており、店主がお茶漬けに浮かべて、京の風情と幸せを運ぶようにと考案されたそうです。400年の伝統の味を皆さん堪能されました。 次に訪れたのは、宗禅さんから東へ100メートルぐらいの所のある西陣織工芸美術館「松翠閣」です。 こちらの町屋では俵屋宗達や尾形光琳などの名匠の屏風や掛軸をはじめ、モネやゴッホといった西洋の巨匠の名画を西陣織で創作して展示されています。
次に訪れたのは、宗禅さんから東へ100メートルぐらいの所のある西陣織工芸美術館「松翠閣」です。 こちらの町屋では俵屋宗達や尾形光琳などの名匠の屏風や掛軸をはじめ、モネやゴッホといった西洋の巨匠の名画を西陣織で創作して展示されています。 
2階にある部屋は壁一面がモネの名画「睡蓮」を正絹(絹)と蓄光糸で織り上げた物で部屋を暗くして絵の模様が浮かび上がってくる幻想的な空間を体験できました。
最後に訪れたのが「織成館」です。ここは手織物や能装束の展示から手織り体験が出来る伝統文化の振興を目的に1989年に西陣の帯製造業「渡文」が設立した町屋の館です。 今日の参加者の中の一人の男性が、私は45年前京都の大学に通学していた頃、この辺りに下宿されていたそうです。この方が西陣も随分変わりましたねとおっしゃったのが印象でした。観光で京都へ来られる方もこのような京都の楽しみ方もあるのだと参考になれば幸いです。
今日の参加者の中の一人の男性が、私は45年前京都の大学に通学していた頃、この辺りに下宿されていたそうです。この方が西陣も随分変わりましたねとおっしゃったのが印象でした。観光で京都へ来られる方もこのような京都の楽しみ方もあるのだと参考になれば幸いです。
 17日の土曜日異業種交流で京都西陣界隈で大人の課外授業をしました。まず最初に訪れたのは、菓匠、茶房、上枝物あられ処「宗禅」です。ここであられ作りを体験しました。築120年の町屋での「あられ作り」です。
17日の土曜日異業種交流で京都西陣界隈で大人の課外授業をしました。まず最初に訪れたのは、菓匠、茶房、上枝物あられ処「宗禅」です。ここであられ作りを体験しました。築120年の町屋での「あられ作り」です。 
このお店、ただのあられ屋さんでは、ありません。京都の洛北で400年以上の歴史のある料亭「山ばな平八茶屋」との合作で誕生した店です。素材のこだわりは、半端ではありません。この日あられ作りの体験をした後に頂いたのは、この店でしか食べられない絶品の「ぶぶ漬け」でした。一般でいうお茶漬けです。
素材は天然の真鯛と国産の鰻で平八茶屋で作られた逸品です。あられは、帆掛けの宝船をかたどっており、店主がお茶漬けに浮かべて、京の風情と幸せを運ぶようにと考案されたそうです。400年の伝統の味を皆さん堪能されました。
 次に訪れたのは、宗禅さんから東へ100メートルぐらいの所のある西陣織工芸美術館「松翠閣」です。 こちらの町屋では俵屋宗達や尾形光琳などの名匠の屏風や掛軸をはじめ、モネやゴッホといった西洋の巨匠の名画を西陣織で創作して展示されています。
次に訪れたのは、宗禅さんから東へ100メートルぐらいの所のある西陣織工芸美術館「松翠閣」です。 こちらの町屋では俵屋宗達や尾形光琳などの名匠の屏風や掛軸をはじめ、モネやゴッホといった西洋の巨匠の名画を西陣織で創作して展示されています。 
2階にある部屋は壁一面がモネの名画「睡蓮」を正絹(絹)と蓄光糸で織り上げた物で部屋を暗くして絵の模様が浮かび上がってくる幻想的な空間を体験できました。

最後に訪れたのが「織成館」です。ここは手織物や能装束の展示から手織り体験が出来る伝統文化の振興を目的に1989年に西陣の帯製造業「渡文」が設立した町屋の館です。
 今日の参加者の中の一人の男性が、私は45年前京都の大学に通学していた頃、この辺りに下宿されていたそうです。この方が西陣も随分変わりましたねとおっしゃったのが印象でした。観光で京都へ来られる方もこのような京都の楽しみ方もあるのだと参考になれば幸いです。
今日の参加者の中の一人の男性が、私は45年前京都の大学に通学していた頃、この辺りに下宿されていたそうです。この方が西陣も随分変わりましたねとおっしゃったのが印象でした。観光で京都へ来られる方もこのような京都の楽しみ方もあるのだと参考になれば幸いです。 Posted by フェラリーの翼 at
22:59
│Comments(0)
2010年04月16日
まだ楽しめる京都の桜 仁和寺の御室桜
仁和寺の遅咲きの「御室桜」今週末が見ごろ 
御室桜は遅咲きの里桜で丈が2m~3mと低いのが特徴です。12日に満開になり、17日、18日が見ごろを迎えます。 京都市右京区御室にある仁和寺は真言宗のお寺で888年(仁和4年)宇多天皇により創建されました。 仁和寺の「御室桜」は大正13年天然記念物に指定され、国の名勝になっています。現代の御室桜は、1696年の伽藍再建の折に植えられた有明という品種で境内に200本以上あります。毎年約10万人の観光客がこの桜を見に訪れるそうです。
京都市右京区御室にある仁和寺は真言宗のお寺で888年(仁和4年)宇多天皇により創建されました。 仁和寺の「御室桜」は大正13年天然記念物に指定され、国の名勝になっています。現代の御室桜は、1696年の伽藍再建の折に植えられた有明という品種で境内に200本以上あります。毎年約10万人の観光客がこの桜を見に訪れるそうです。 

御室桜は遅咲きの里桜で丈が2m~3mと低いのが特徴です。12日に満開になり、17日、18日が見ごろを迎えます。
 京都市右京区御室にある仁和寺は真言宗のお寺で888年(仁和4年)宇多天皇により創建されました。 仁和寺の「御室桜」は大正13年天然記念物に指定され、国の名勝になっています。現代の御室桜は、1696年の伽藍再建の折に植えられた有明という品種で境内に200本以上あります。毎年約10万人の観光客がこの桜を見に訪れるそうです。
京都市右京区御室にある仁和寺は真言宗のお寺で888年(仁和4年)宇多天皇により創建されました。 仁和寺の「御室桜」は大正13年天然記念物に指定され、国の名勝になっています。現代の御室桜は、1696年の伽藍再建の折に植えられた有明という品種で境内に200本以上あります。毎年約10万人の観光客がこの桜を見に訪れるそうです。 
Posted by フェラリーの翼 at
13:51
│Comments(1)
2010年04月15日
世界遺産 銀閣寺の修復が完了
銀閣寺(慈照寺)の修復が完了 12日に落慶法要が営まれた 観音殿に黒漆塗りの輝きが戻る  京都市左京区にある世界文化遺産の銀閣寺(慈照寺)が1981年以来30年ぶりに修復され、12日に落慶法要が同寺で営まれた。金閣寺と比べると少し地味なイメージがあるが、京都へ修学旅行に訪れる学生や外人観光客ならば必ずと言っていいほど訪れる人気のある銀閣寺、この寺は1489年(延徳元年)に室町幕府の8代将軍足利義政によって建立され、東山文化の象徴とされています。
京都市左京区にある世界文化遺産の銀閣寺(慈照寺)が1981年以来30年ぶりに修復され、12日に落慶法要が同寺で営まれた。金閣寺と比べると少し地味なイメージがあるが、京都へ修学旅行に訪れる学生や外人観光客ならば必ずと言っていいほど訪れる人気のある銀閣寺、この寺は1489年(延徳元年)に室町幕府の8代将軍足利義政によって建立され、東山文化の象徴とされています。
 京都市左京区にある世界文化遺産の銀閣寺(慈照寺)が1981年以来30年ぶりに修復され、12日に落慶法要が同寺で営まれた。金閣寺と比べると少し地味なイメージがあるが、京都へ修学旅行に訪れる学生や外人観光客ならば必ずと言っていいほど訪れる人気のある銀閣寺、この寺は1489年(延徳元年)に室町幕府の8代将軍足利義政によって建立され、東山文化の象徴とされています。
京都市左京区にある世界文化遺産の銀閣寺(慈照寺)が1981年以来30年ぶりに修復され、12日に落慶法要が同寺で営まれた。金閣寺と比べると少し地味なイメージがあるが、京都へ修学旅行に訪れる学生や外人観光客ならば必ずと言っていいほど訪れる人気のある銀閣寺、この寺は1489年(延徳元年)に室町幕府の8代将軍足利義政によって建立され、東山文化の象徴とされています。 Posted by フェラリーの翼 at
23:22
│Comments(0)
2010年04月14日
気温の話・・・私達の生活にとても大切な事です。
4月も中旬というのに街中で、すれ違うお年寄りの会話を聞いていると、「いつまでも寒いですね」という言葉をよく耳にします。そこで今日は「気温」の話をしたいと思います。気温と言えばTVの天気予報を思い浮かべる方が多いと思います。その天気予報で一番大事なのが気温なのです。気温に関する用語は沢山あります。寒さがゆるむとか、寒気、寒波、不快指数、放射冷却、大気の状態が不安定、真冬日、真夏日、寒の戻り、フェーン現象、熱帯夜、これの他にもまだまだあります。いずれも気象予報士が天気予報の中で、よく使っている言葉ばかりです。例えば冬の終り頃に三寒四温とよく言いますね。これは、その時期に3日間ほど寒い日が続き、次の4日間は暖かく、この状態が繰り返されることを言います。さて「気温」の話に戻りましょう。タイトルで書いたように、気温は私達の生活にとつてとても大切なことなのです。食べ物である農作物の収穫や私達の健康(インフルエンザの流行も気温と湿度が関係しています)や企業のビジネスに一番影響を与えるのが気温なのです。  そもそも「気温」とは大気の温度のことを言います。気象台の観測要素でも「気温」と「降水」は重要な事とされています。気温の単位は摂氏(℃)で表します。しかしアメリカでは違います。華氏という単位で表します。摂氏で表した温度に1.8を掛けて32をを足すと華氏の温度になります。また気象学では、絶対温度(K)という単位がよく使われます。これは摂氏で表した温度に273.15を足すと絶対温度になります。WMO(世界気象機関)の取り決めで地上気象観測では、気温の測定は地表面1.25m~2.0mの高さで観測する事を基準としています。日本では気象庁で測定される気温は、地上から1.5mの高さを基準にしています。以前ブログで取り上げた百葉箱の事覚えておられるでしょうか。あの百葉箱の中に気温を測る温度計が入っています。温度計にはアルコール温度計と水銀温度計が広く一般に使われています。これらの温度計の気温を測る仕組みは、アルコールや水銀などの流体の体積が温度によって変化するという性質を利用して大気の温度を計測しているのです。気象庁(国土交通省管轄)では電気式温度計を使用して気温の計測をしています。この温度計の仕組みは、金属の抵抗が温度によって変化するという性質を利用しているのです。気温は高度が高くなるにつれて下がっていきます。これは地表に近い対流圏では、太陽の放射熱によって地表が暖められ、暖まった地表が大気を暖めるというプロセスを経るからです。 今、世界中で地球の温暖化とか異常気象が問題になっています。気象データーは、インターネットから取得する事が出来ます。無料で検索及び閲覧できる公的機関のWebサイトをご紹介しましょう。 NASA GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP) NASA(アメリカ航空宇宙局)の下部組織ゴダード宇宙科学研究所が提供する気候変動に関するデーターベースです。世界各地の約7,350地点から観測したデーターです。
そもそも「気温」とは大気の温度のことを言います。気象台の観測要素でも「気温」と「降水」は重要な事とされています。気温の単位は摂氏(℃)で表します。しかしアメリカでは違います。華氏という単位で表します。摂氏で表した温度に1.8を掛けて32をを足すと華氏の温度になります。また気象学では、絶対温度(K)という単位がよく使われます。これは摂氏で表した温度に273.15を足すと絶対温度になります。WMO(世界気象機関)の取り決めで地上気象観測では、気温の測定は地表面1.25m~2.0mの高さで観測する事を基準としています。日本では気象庁で測定される気温は、地上から1.5mの高さを基準にしています。以前ブログで取り上げた百葉箱の事覚えておられるでしょうか。あの百葉箱の中に気温を測る温度計が入っています。温度計にはアルコール温度計と水銀温度計が広く一般に使われています。これらの温度計の気温を測る仕組みは、アルコールや水銀などの流体の体積が温度によって変化するという性質を利用して大気の温度を計測しているのです。気象庁(国土交通省管轄)では電気式温度計を使用して気温の計測をしています。この温度計の仕組みは、金属の抵抗が温度によって変化するという性質を利用しているのです。気温は高度が高くなるにつれて下がっていきます。これは地表に近い対流圏では、太陽の放射熱によって地表が暖められ、暖まった地表が大気を暖めるというプロセスを経るからです。 今、世界中で地球の温暖化とか異常気象が問題になっています。気象データーは、インターネットから取得する事が出来ます。無料で検索及び閲覧できる公的機関のWebサイトをご紹介しましょう。 NASA GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP) NASA(アメリカ航空宇宙局)の下部組織ゴダード宇宙科学研究所が提供する気候変動に関するデーターベースです。世界各地の約7,350地点から観測したデーターです。
 そもそも「気温」とは大気の温度のことを言います。気象台の観測要素でも「気温」と「降水」は重要な事とされています。気温の単位は摂氏(℃)で表します。しかしアメリカでは違います。華氏という単位で表します。摂氏で表した温度に1.8を掛けて32をを足すと華氏の温度になります。また気象学では、絶対温度(K)という単位がよく使われます。これは摂氏で表した温度に273.15を足すと絶対温度になります。WMO(世界気象機関)の取り決めで地上気象観測では、気温の測定は地表面1.25m~2.0mの高さで観測する事を基準としています。日本では気象庁で測定される気温は、地上から1.5mの高さを基準にしています。以前ブログで取り上げた百葉箱の事覚えておられるでしょうか。あの百葉箱の中に気温を測る温度計が入っています。温度計にはアルコール温度計と水銀温度計が広く一般に使われています。これらの温度計の気温を測る仕組みは、アルコールや水銀などの流体の体積が温度によって変化するという性質を利用して大気の温度を計測しているのです。気象庁(国土交通省管轄)では電気式温度計を使用して気温の計測をしています。この温度計の仕組みは、金属の抵抗が温度によって変化するという性質を利用しているのです。気温は高度が高くなるにつれて下がっていきます。これは地表に近い対流圏では、太陽の放射熱によって地表が暖められ、暖まった地表が大気を暖めるというプロセスを経るからです。 今、世界中で地球の温暖化とか異常気象が問題になっています。気象データーは、インターネットから取得する事が出来ます。無料で検索及び閲覧できる公的機関のWebサイトをご紹介しましょう。 NASA GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP) NASA(アメリカ航空宇宙局)の下部組織ゴダード宇宙科学研究所が提供する気候変動に関するデーターベースです。世界各地の約7,350地点から観測したデーターです。
そもそも「気温」とは大気の温度のことを言います。気象台の観測要素でも「気温」と「降水」は重要な事とされています。気温の単位は摂氏(℃)で表します。しかしアメリカでは違います。華氏という単位で表します。摂氏で表した温度に1.8を掛けて32をを足すと華氏の温度になります。また気象学では、絶対温度(K)という単位がよく使われます。これは摂氏で表した温度に273.15を足すと絶対温度になります。WMO(世界気象機関)の取り決めで地上気象観測では、気温の測定は地表面1.25m~2.0mの高さで観測する事を基準としています。日本では気象庁で測定される気温は、地上から1.5mの高さを基準にしています。以前ブログで取り上げた百葉箱の事覚えておられるでしょうか。あの百葉箱の中に気温を測る温度計が入っています。温度計にはアルコール温度計と水銀温度計が広く一般に使われています。これらの温度計の気温を測る仕組みは、アルコールや水銀などの流体の体積が温度によって変化するという性質を利用して大気の温度を計測しているのです。気象庁(国土交通省管轄)では電気式温度計を使用して気温の計測をしています。この温度計の仕組みは、金属の抵抗が温度によって変化するという性質を利用しているのです。気温は高度が高くなるにつれて下がっていきます。これは地表に近い対流圏では、太陽の放射熱によって地表が暖められ、暖まった地表が大気を暖めるというプロセスを経るからです。 今、世界中で地球の温暖化とか異常気象が問題になっています。気象データーは、インターネットから取得する事が出来ます。無料で検索及び閲覧できる公的機関のWebサイトをご紹介しましょう。 NASA GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP) NASA(アメリカ航空宇宙局)の下部組織ゴダード宇宙科学研究所が提供する気候変動に関するデーターベースです。世界各地の約7,350地点から観測したデーターです。 Posted by フェラリーの翼 at
21:28
│Comments(0)
2010年04月12日
ー陶ー 神山易久展・・・髙島屋大阪店にて開催中。
神山易久展に行ってきました。 
 9日の午後大阪灘波の髙島屋大阪店6階美術画廊で開かれています神山先生の作品を見に行って来ました。先生にお目にかかるのは、昨年9月以来2度目です。須恵毛能(すえもの)信楽のやきものは釉薬をかけず穴釜でゆつくりと還元焼成された須恵器の流れをくむものだそうです。須恵器は中国の南部地方で生まれ、5世紀に朝鮮半島の南部から多くの渡来人によつて日本に伝えられ、信楽など六古窯をはじめ各地に広がり和風化されたとのことです。先生の作品を拝見して感じるのは、躍動的なアート、和と洋の融合を感じます。会場には中本若枝先生もおられました。夜近くにあるホテルモントレーで神山先生を囲んで夕食会があり、参加させて頂き、この食事会には仏師の方や陶芸家、京都で建築を研究されているフランス人女性など、いろんなジャンルの方々が参加されており、神山先生のお話や、皆さんのお仕事の話を拝聴することが出来、本当に楽しいひと時を過ごすことが出来ました。この作品店は13日(火)まで開催されております。先生は今年の夏アメリカのボストンで作品展をされるとのお話でした。
9日の午後大阪灘波の髙島屋大阪店6階美術画廊で開かれています神山先生の作品を見に行って来ました。先生にお目にかかるのは、昨年9月以来2度目です。須恵毛能(すえもの)信楽のやきものは釉薬をかけず穴釜でゆつくりと還元焼成された須恵器の流れをくむものだそうです。須恵器は中国の南部地方で生まれ、5世紀に朝鮮半島の南部から多くの渡来人によつて日本に伝えられ、信楽など六古窯をはじめ各地に広がり和風化されたとのことです。先生の作品を拝見して感じるのは、躍動的なアート、和と洋の融合を感じます。会場には中本若枝先生もおられました。夜近くにあるホテルモントレーで神山先生を囲んで夕食会があり、参加させて頂き、この食事会には仏師の方や陶芸家、京都で建築を研究されているフランス人女性など、いろんなジャンルの方々が参加されており、神山先生のお話や、皆さんのお仕事の話を拝聴することが出来、本当に楽しいひと時を過ごすことが出来ました。この作品店は13日(火)まで開催されております。先生は今年の夏アメリカのボストンで作品展をされるとのお話でした。

 9日の午後大阪灘波の髙島屋大阪店6階美術画廊で開かれています神山先生の作品を見に行って来ました。先生にお目にかかるのは、昨年9月以来2度目です。須恵毛能(すえもの)信楽のやきものは釉薬をかけず穴釜でゆつくりと還元焼成された須恵器の流れをくむものだそうです。須恵器は中国の南部地方で生まれ、5世紀に朝鮮半島の南部から多くの渡来人によつて日本に伝えられ、信楽など六古窯をはじめ各地に広がり和風化されたとのことです。先生の作品を拝見して感じるのは、躍動的なアート、和と洋の融合を感じます。会場には中本若枝先生もおられました。夜近くにあるホテルモントレーで神山先生を囲んで夕食会があり、参加させて頂き、この食事会には仏師の方や陶芸家、京都で建築を研究されているフランス人女性など、いろんなジャンルの方々が参加されており、神山先生のお話や、皆さんのお仕事の話を拝聴することが出来、本当に楽しいひと時を過ごすことが出来ました。この作品店は13日(火)まで開催されております。先生は今年の夏アメリカのボストンで作品展をされるとのお話でした。
9日の午後大阪灘波の髙島屋大阪店6階美術画廊で開かれています神山先生の作品を見に行って来ました。先生にお目にかかるのは、昨年9月以来2度目です。須恵毛能(すえもの)信楽のやきものは釉薬をかけず穴釜でゆつくりと還元焼成された須恵器の流れをくむものだそうです。須恵器は中国の南部地方で生まれ、5世紀に朝鮮半島の南部から多くの渡来人によつて日本に伝えられ、信楽など六古窯をはじめ各地に広がり和風化されたとのことです。先生の作品を拝見して感じるのは、躍動的なアート、和と洋の融合を感じます。会場には中本若枝先生もおられました。夜近くにあるホテルモントレーで神山先生を囲んで夕食会があり、参加させて頂き、この食事会には仏師の方や陶芸家、京都で建築を研究されているフランス人女性など、いろんなジャンルの方々が参加されており、神山先生のお話や、皆さんのお仕事の話を拝聴することが出来、本当に楽しいひと時を過ごすことが出来ました。この作品店は13日(火)まで開催されております。先生は今年の夏アメリカのボストンで作品展をされるとのお話でした。 Posted by フェラリーの翼 at
01:06
│Comments(0)
2010年04月09日
放置自転車が街から消える日は果たしてやって来るのか。
 駅前や街のスーパーなどの人の往来が多い所の放置自転車を見る度に私は思うのですが、撤去されてたと思った矢先また多くの自転車が道路を占領しています。一人の迷惑行為がまぁいいかと誰も彼もがやっていまい放置自転車の問題がいつまで経っても解決しません。放置自転車は今の世の中を象徴しています。よく何々は世の中が悪いなどと言いますが、放置自転車は、私達がやってしまった迷惑の大きな塊ではないでしょうか。地方自治体や市町村がいくら対策をしても解決できないと思います。この問題を解決できるのは、その原因を作った私達しかありません。ゴミの問題も然りです。何か問題が起これば役所に委ねるのではなく、私達住民が少し注意すえば解決出来る事は、いっぱいあると思います。自分は迷惑行為はしていないから関係ないではなく、気が付けば、よくなるように協力して行けば、きっと今よりも住みやすい環境になるのではと私は思います。誰しも自立した人間が孤立した人間にはなりたくありませんから。
駅前や街のスーパーなどの人の往来が多い所の放置自転車を見る度に私は思うのですが、撤去されてたと思った矢先また多くの自転車が道路を占領しています。一人の迷惑行為がまぁいいかと誰も彼もがやっていまい放置自転車の問題がいつまで経っても解決しません。放置自転車は今の世の中を象徴しています。よく何々は世の中が悪いなどと言いますが、放置自転車は、私達がやってしまった迷惑の大きな塊ではないでしょうか。地方自治体や市町村がいくら対策をしても解決できないと思います。この問題を解決できるのは、その原因を作った私達しかありません。ゴミの問題も然りです。何か問題が起これば役所に委ねるのではなく、私達住民が少し注意すえば解決出来る事は、いっぱいあると思います。自分は迷惑行為はしていないから関係ないではなく、気が付けば、よくなるように協力して行けば、きっと今よりも住みやすい環境になるのではと私は思います。誰しも自立した人間が孤立した人間にはなりたくありませんから。Posted by フェラリーの翼 at
18:56
│Comments(0)
2010年04月07日
季節を感じる 懐かしい歌・・・キャンディーズの春一番
 人には、その季節、季節に懐かしい歌、思い出の歌があると思います。私が春になると聞きたくなる歌は1976年3月に発売されたレコード キャンディーズの「春一番」ですね。春に因んだ曲を思い浮かべてみると柏原芳恵の春なのに、イルカのなごり雪、石野真子の春ラ!ラ!ラ!、松任谷由美の春よ来い、松田聖子の赤いスイートピー、スピッツの春の歌がありました。歌は過去の記憶を辿る手懸かりのような気がしてなりません。貴方の季節に纏わる歌はどんな曲ですか。
人には、その季節、季節に懐かしい歌、思い出の歌があると思います。私が春になると聞きたくなる歌は1976年3月に発売されたレコード キャンディーズの「春一番」ですね。春に因んだ曲を思い浮かべてみると柏原芳恵の春なのに、イルカのなごり雪、石野真子の春ラ!ラ!ラ!、松任谷由美の春よ来い、松田聖子の赤いスイートピー、スピッツの春の歌がありました。歌は過去の記憶を辿る手懸かりのような気がしてなりません。貴方の季節に纏わる歌はどんな曲ですか。 Posted by フェラリーの翼 at
18:56
│Comments(0)

 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン