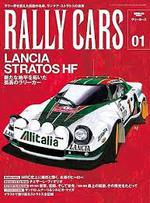2007年03月29日
都をどりの「もったいない」が限定販売!
今年の「第135回都をどり」は4月1日から4月30日まで祇園甲部歌舞練場で行われます。第1回は明治5年(1872年)に始まり100年以上続いています。花街のをどりは、宮川町の京をどり、上七軒の北野をどり、先斗町の鴨川をどりと4月、5月の京都は、まさに「春らんまん」です。  さて本日のテーマの話をいたします。 都をどりの衣装は1着限りのデザインで作られ、かっては期間中120回の公演が終わると、すべて焼却していました。ところが10年ぐらい前から「もったいない」 と約200着の衣装を保管してきました。 今年15着の衣装を加工してテイッシュケース1個800円(限定300個)と巾着袋1個1,500円(限定150個)を限定販売することになりました。都をどりファンには、たまりませんね。
さて本日のテーマの話をいたします。 都をどりの衣装は1着限りのデザインで作られ、かっては期間中120回の公演が終わると、すべて焼却していました。ところが10年ぐらい前から「もったいない」 と約200着の衣装を保管してきました。 今年15着の衣装を加工してテイッシュケース1個800円(限定300個)と巾着袋1個1,500円(限定150個)を限定販売することになりました。都をどりファンには、たまりませんね。
 都をどりのHP http://www.miyako-odori.jp/top.html
都をどりのHP http://www.miyako-odori.jp/top.html
 さて本日のテーマの話をいたします。 都をどりの衣装は1着限りのデザインで作られ、かっては期間中120回の公演が終わると、すべて焼却していました。ところが10年ぐらい前から「もったいない」 と約200着の衣装を保管してきました。 今年15着の衣装を加工してテイッシュケース1個800円(限定300個)と巾着袋1個1,500円(限定150個)を限定販売することになりました。都をどりファンには、たまりませんね。
さて本日のテーマの話をいたします。 都をどりの衣装は1着限りのデザインで作られ、かっては期間中120回の公演が終わると、すべて焼却していました。ところが10年ぐらい前から「もったいない」 と約200着の衣装を保管してきました。 今年15着の衣装を加工してテイッシュケース1個800円(限定300個)と巾着袋1個1,500円(限定150個)を限定販売することになりました。都をどりファンには、たまりませんね。  都をどりのHP http://www.miyako-odori.jp/top.html
都をどりのHP http://www.miyako-odori.jp/top.html Posted by フェラリーの翼 at
23:40
│Comments(0)
2007年03月28日
切手とめぐる京都
つい最近こんな切手が発売され買いました。いままでに京都の名所などが切手の図案になつた事はありましが、今回は京都が切手になったという感じです。私は中学1年の頃から切手を集めるようになりました。そして今でも集めています。ですから、かなりの枚数の切手を持っています。80円切手が12枚で 図案は、舞妓、秋の三千院、金閣寺、桜満開の清水寺の舞台、渡月橋、御室仁和寺、木津の流れ橋、秋の紅葉の東福寺の通天橋、伏見の酒蔵です。まさに京都が切手になりました。  クリックすると大きくなります。
クリックすると大きくなります。
 クリックすると大きくなります。
クリックすると大きくなります。 Posted by フェラリーの翼 at
23:55
│Comments(0)
2007年03月26日
キャベツが身体にいい話です。
今日は、おそらく皆さんが毎日食べているキャベツの話です。 とても為になるので、特に女性の方、ダイエットがうまくできない方に必見ですよ。 みなさんは、普段キャベツをどのようにしてたべていますか。揚げ物の付け合せ、サラダ、お好み焼き、ロールキャベツなどでしょうか。キャベツの起源は地中海沿岸やヨーロッパの大西洋沿岸の岩場に自生していた野生種から進化したものと考えられます。青汁で、おなじみケールの一種です。アブラナ科の植物で漢名を「甘藍」といい、日本には、1709年オランダ人によって長崎に伝来したそうで、最初の頃は、主に観賞用の葉牡丹として栽培され、その後大正時代に品種改良され現在のキャベツになりました。実はキャベツには旬がありません。キャベツの種類を見てみると、寒玉、春玉(新キャベツ)、紫キャベツ、グリーンボール、高原キャベツ、サボイキャベツ、ゴールドサワーなど1年中収穫されています。国内の産地では、愛知、群馬、千葉がおもな産地です。 キャベツは、からだには、たいへん良いオールシーズン食べられる野菜なのです。 まず栄養面で言いますとビタミンC、食物繊維が多く含まれ、カルシウム、ビタミンU、カロテンなども含まれています。ですから、女性に多い便秘やダイエットにはベストな食物(100gあたり23Kcal)と言えます。ダイエットの場合は、食前にキャベツを食べると満腹感があり食事の量が減らすことができ、食べながらダイエットする事により、リバンドのない正しいダイエットができるのです。 どうです。キャベツの実力は、すごいでしょう。  たかがキャベツ、されどキャベツですね。
たかがキャベツ、されどキャベツですね。
 たかがキャベツ、されどキャベツですね。
たかがキャベツ、されどキャベツですね。 Posted by フェラリーの翼 at
19:59
│Comments(0)
2007年03月25日
インフルエンザ治療薬 タミフルについての私の意見
今年の冬は、暖冬であったのでインフルエンザのパンデミックは、今のところはありません。連日新聞の紙面には、タミフルの関連記事を目にします。記事を見るたび厚生労働省の、またはわが国の医療行政の信頼性の低いことに呆れます。ブログのテーマにタミフルのことを書くのは不謹慎とは思うのですが、自分の意見を書くことにしました。まずタミフルはどんな薬か、わが国の現状はどうかを説明します。タミフルとは、抗インフルエンザウイルス剤で、A型、B型のインフルエンザウイルスの増殖を抑える効果があり、また鳥インフルエンザにも効果が見込まれるとされておます。タミフルの原料は、中華料理のスパイス「八角」です。八角から抽出されるシキミ酸、成分はリン酸オセルタビルと言います。民フルも薬価は1カプセルあたり363.7円ですから原料の八角の市販価格から計算すると実に約39倍になります。ちなみに八角を食べたからといって効くわけではありません。この薬はスイスのロシュ社が製造元で、特許はアメリカのギリアド・サイエンシズ社が持ち、日本では中外製薬が輸入販売しています。ロシュ社のデーターによると全世界でタミフルは約3200万人が服用し、なんと2400万人は日本で服用されています。タミフルは、インフルエンザの発症から48時間以内に服用しないと効果がないとされています。この薬の副作用は確認されているだけだも20以上あります。つまりタミフルは、きわめて深刻な副作用のあるリスクの高いお薬なのです。そして必ずしもインフルエンザの特効薬ではないと言えます。医師の中にもその使用について賛否があります。厚生労働省の対応には、呆れるばかりです。そもそもインフルエンザは、予防できる疾患です。予防医療をなぜもっと進めないのか疑問に思います。国内の大手の製薬会社の合併や統合は、新薬の開発よりも利益追求が優先してるのではないのでしょうか。タミフルについては、乳児の脳症などまだまだ色々な問題が出てくる可能性があります。日本が美しい国にする前に情けない国と諸外国から言われないように、したいと願うばかりです。
Posted by フェラリーの翼 at
16:55
│Comments(0)
2007年03月22日
春は牡丹、秋は萩、お彼岸との関係は?
今日は、お彼岸のお中日でした。家族でお墓参りに行かれた方が沢山おられたと思います。お彼岸は1年に2回あり、春のお彼岸と秋のお彼岸、彼岸は仏教の行事ですが、日本独特の行事で世界の他の仏教の国では、ありません。一般に「お彼岸」は春の彼岸の事を言います。秋の彼岸は、本当は「後の彼岸」と言います。彼岸は、太陽が真東から昇り、真西に沈む日、昼と夜の長さが同じ日と定義されています。
タイトルの牡丹と萩とお彼岸の関係は 春のお彼岸には、ぼた餅を秋のお彼岸には、おはぎを食べますよね。ぼた餅とおはぎは、実は、同じ物で、違うのは食べる時期だけなのです。「暑さ、寒さも彼岸まで」と言います。これは春の彼岸は農作業が始まる時期で、秋の彼岸は収穫の時期にあたるのです。ぼた餅やおはぎは春の牡丹が咲く頃、秋の萩の花が咲く頃がお彼岸の時期になるからです。
彼岸は、仏教では彼の岸として悟りの境地を言い、苦しみに満ちている比岸と対になる言葉として使われます。彼岸にご先祖の霊を敬いお墓参りをする習慣。今日私たちが安心して暮らせているのは、ご先祖様の御蔭です。感謝の心をいつも持ち続けたいと願うばかりです。ちなみにお墓参りは江戸時代から始まったそうです。
タイトルの牡丹と萩とお彼岸の関係は 春のお彼岸には、ぼた餅を秋のお彼岸には、おはぎを食べますよね。ぼた餅とおはぎは、実は、同じ物で、違うのは食べる時期だけなのです。「暑さ、寒さも彼岸まで」と言います。これは春の彼岸は農作業が始まる時期で、秋の彼岸は収穫の時期にあたるのです。ぼた餅やおはぎは春の牡丹が咲く頃、秋の萩の花が咲く頃がお彼岸の時期になるからです。
彼岸は、仏教では彼の岸として悟りの境地を言い、苦しみに満ちている比岸と対になる言葉として使われます。彼岸にご先祖の霊を敬いお墓参りをする習慣。今日私たちが安心して暮らせているのは、ご先祖様の御蔭です。感謝の心をいつも持ち続けたいと願うばかりです。ちなみにお墓参りは江戸時代から始まったそうです。

Posted by フェラリーの翼 at
00:02
│Comments(0)
2007年03月20日
早春の味 いかなごの釘煮は、釘を入れて煮るの?
いかなごの釘煮は、神戸や明石あたりでは、この時期家庭で作る料理、春の風物詩です。 「いかなごの釘煮」関西では、みんな知っていますね。でも 何故 釘煮というのか?いかなごとしらすはおなじ魚ではないのか?疑問に思いませんか。 釘煮とは釘を入れて佃煮にするのではなく、煮詰めて、出来上がった その姿が曲がって錆びた釘に似ているから、そう呼ばれるようになりました。いかなごは学名を「玉筋魚」と書いていかなごと読みます。スズキ目イカナゴ科の魚です。しらすとは別の魚です。1年魚をシンコ(新子)と呼び、2年魚をフルセ(古背)と呼びます。 釘煮のルーツは、昭和24年頃明石にあった県の水産試験場でいかなごの佃煮を作ってところ砂糖と醤油だけ作る昔からの製法に水飴を加え甘味のある独特の味を開発して、その出来上がりの色艶から、当時は「紅梅煮」と呼ばれていたそうです。 炊きたてのご飯で食べると美味しいですね。 

Posted by フェラリーの翼 at
23:12
│Comments(0)
2007年03月17日
小野小町ゆかりの寺で、はねず踊りと今様。
小野小町と「はねず踊り」 3月25日(日)京都山科小野にある小野小町ゆかりの寺、随心院で「はねず踊り」が行われます。「はねず」とは薄紅色のことではねず色の梅が咲く頃、小野小町と深草の少将との恋物語をわらべ歌とともに、少女たちが踊ります。 
 少将さまでござる 深草からでござる 雪の夜みちを とぼとぼとござる 今日でどうやら 九十と九夜 百夜まだでも まぁおはいりと あけてびっくり よー おかわりじゃ
少将さまでござる 深草からでござる 雪の夜みちを とぼとぼとござる 今日でどうやら 九十と九夜 百夜まだでも まぁおはいりと あけてびっくり よー おかわりじゃ

 少将さまでござる 深草からでござる 雪の夜みちを とぼとぼとござる 今日でどうやら 九十と九夜 百夜まだでも まぁおはいりと あけてびっくり よー おかわりじゃ
少将さまでござる 深草からでござる 雪の夜みちを とぼとぼとござる 今日でどうやら 九十と九夜 百夜まだでも まぁおはいりと あけてびっくり よー おかわりじゃ Posted by フェラリーの翼 at
21:17
│Comments(0)
2007年03月14日
お水取り限定の和菓子 「糊こぼし」
奈良・東大寺二月堂の伝統行事「お水取り」は今年でなんと1256回目、大仏が開眼した752年から途切れなく続く伝統行事なのです。12日の夜、長さ8m,重さ約60キロもある籠松明11本が二月堂の舞台を駆けるクライマックスを迎えた。この日の気温は4.3度の寒さ。境内を埋めた参拝者は約3万3000人、松明の火の粉が勇壮に夜空を焦がし観客を魅了しました。13日未明には、二月堂下の閼伽井屋にある井戸から、神聖な「香水(こうずい)」を汲む「お水取り」があり、修二会は、15日未明に満行を迎えます。 このお水取りの期間のみに発売される和菓子があるのを、ご存知でしょうか。萬々堂通則の「糊こぼし」という名の和菓子です。花びらは練切で作られていて、形はまさに「お水取り」で使用される和紙製の「糊こぼし」そのものです。
このお水取りの期間のみに発売される和菓子があるのを、ご存知でしょうか。萬々堂通則の「糊こぼし」という名の和菓子です。花びらは練切で作られていて、形はまさに「お水取り」で使用される和紙製の「糊こぼし」そのものです。

 このお水取りの期間のみに発売される和菓子があるのを、ご存知でしょうか。萬々堂通則の「糊こぼし」という名の和菓子です。花びらは練切で作られていて、形はまさに「お水取り」で使用される和紙製の「糊こぼし」そのものです。
このお水取りの期間のみに発売される和菓子があるのを、ご存知でしょうか。萬々堂通則の「糊こぼし」という名の和菓子です。花びらは練切で作られていて、形はまさに「お水取り」で使用される和紙製の「糊こぼし」そのものです。

Posted by フェラリーの翼 at
23:55
│Comments(0)
2007年03月11日
毛筆書道のライバルが登場!その名はカリグラフィー
カリグラフィーとは 文字を書く。私たち日本人には「毛筆書道」があります。カリグラフィーとは「西洋書道」アルファベットの書道ともいわれています。手描きで描くクラシカルなデザイン文字です。すでに全国には、カルチャ教室としてカリグラフィ教室が沢山あり、静かなブームとなっています。書体のバリエーションによりPCでは、ブログにも登場しています。 写真はウエルカムボードの類です。今のライフスタイルにハマル文字だと思いました。 

Posted by フェラリーの翼 at
23:13
│Comments(0)
2007年03月11日
めだかの学校の春
春といえば学校の入学式ですね。めだかの学校について調べてみると全国に意外とありました。今日ご紹介するのは岡山県にある「めだかの学校」です。環境省は、平成11年の2月にめだかを絶滅危惧種に指定しました。岡山県の建部町のある「めだかの学校」は環境学習センターでめだかの飼育室や淡水魚水族館などの展示が見られるそうです。  場所は 岡山県岡山市建部町上609 建部町環境学習センター「めだかの学校」 TEL 0867-22-1231
場所は 岡山県岡山市建部町上609 建部町環境学習センター「めだかの学校」 TEL 0867-22-1231
 場所は 岡山県岡山市建部町上609 建部町環境学習センター「めだかの学校」 TEL 0867-22-1231
場所は 岡山県岡山市建部町上609 建部町環境学習センター「めだかの学校」 TEL 0867-22-1231 Posted by フェラリーの翼 at
01:10
│Comments(0)
2007年03月06日
3月6日 今日は何の日でしょうか?
3月6日今日は「啓蟄」です。 「啓蟄」とは1年を24に分けた季節を表す言葉「二十四節季」その中のひとつが「啓蟄」です。その意味は冬眠していた地中の虫が春になると穴を開けて動き出す日のことを言います。 駅のポスターも衣がえ、春へ春へ!  春の風に誘われて、さくら色の京都へ
春の風に誘われて、さくら色の京都へ
 春の風に誘われて、さくら色の京都へ
春の風に誘われて、さくら色の京都へ Posted by フェラリーの翼 at
22:20
│Comments(0)
2007年03月04日
中国では、今年は60年に1回の「金猪年」すごい。
 中国では、今年は空前の出産ラッシュのベビーブームになりそうです。この訳は、中国では2007年つまり今年60年に1度の「金猪年」中国では「黄金豚年」といって、この年に生まれた赤ちゃんは、将来金持ちになるといわれています。中国のお正月「春節祭」は2月18日でした。日本では今年は干支は猪年ですが、中国では猪は豚のことをいいます。つまり今年は60年に1度廻ってくる黄金の豚年に当たるのです。最近の中国の新聞によると昨年1年間で北京で生まれた赤ちゃんは12万9000人でしたが、今年は少なくても14万人は突破すると予側されています。日本が今少子化が問題になつている現状を考えると、今はすべてが中国に風が吹いているような気がいます。今回のベビーブームによる経済効果もすごく、赤ちゃん用品市場が急速に拡大して、2007年だけで赤ちゃんの使う哺乳瓶の売上げ予想が350億人民元(5250億円)といわれています。わが国の政府も少子高齢化を議論する以前に女性が安心して赤ちゃんを産み、育てられる社会環境作りとシステム、ワーキングプアー、セイフティネットの中身の充実など憲法で保障された最低限度の健康な生活ができる環境をまず第1に取り組んでほしいと願うばかりです。 写真は今年の中国のカレンダーです。
中国では、今年は空前の出産ラッシュのベビーブームになりそうです。この訳は、中国では2007年つまり今年60年に1度の「金猪年」中国では「黄金豚年」といって、この年に生まれた赤ちゃんは、将来金持ちになるといわれています。中国のお正月「春節祭」は2月18日でした。日本では今年は干支は猪年ですが、中国では猪は豚のことをいいます。つまり今年は60年に1度廻ってくる黄金の豚年に当たるのです。最近の中国の新聞によると昨年1年間で北京で生まれた赤ちゃんは12万9000人でしたが、今年は少なくても14万人は突破すると予側されています。日本が今少子化が問題になつている現状を考えると、今はすべてが中国に風が吹いているような気がいます。今回のベビーブームによる経済効果もすごく、赤ちゃん用品市場が急速に拡大して、2007年だけで赤ちゃんの使う哺乳瓶の売上げ予想が350億人民元(5250億円)といわれています。わが国の政府も少子高齢化を議論する以前に女性が安心して赤ちゃんを産み、育てられる社会環境作りとシステム、ワーキングプアー、セイフティネットの中身の充実など憲法で保障された最低限度の健康な生活ができる環境をまず第1に取り組んでほしいと願うばかりです。 写真は今年の中国のカレンダーです。 Posted by フェラリーの翼 at
23:09
│Comments(0)
2007年03月03日
流し雛は子供の無病息災を祈る神事
今日3月3日は桃の節句。京都の下鴨神社では、境内にあるみたらし川に編んだ藁に乗せた雛人形を流し子供たちの無病息災を祈る神事が行われました。

Posted by フェラリーの翼 at
18:26
│Comments(0)
 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン